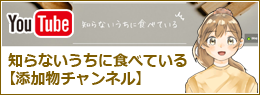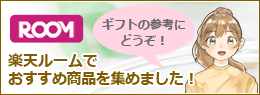遺伝子組み換え表示を見ないで買うと危険?

表示制度の基本的な考え方

遺伝子組換え表示制度の基本的な考え方というのは、どのような方針の制度なのでしょうか?
報告書の冒頭には、3つ書かれていました。
(1) この制度は、消費者が食品を選択する際に、必要な情報を提供することを目的としているため、消費者が求める情報をできる限り分かりやすく表示しなくてはならないこと。同時に事業者の実行可能性やコストも考慮しなければならないこと
(2) 日本国内で流通している全ての遺伝子組み換え農産物は、厚生労働省の安全性審査を受けた安全性が確保されたものであり、遺伝子組み換えの表示は、この安全性が保たれたうえで、消費者の自主的かつ合理的な選択の機会を実現するためのものであること
(3) 遺伝子組換え食品の表示への消費者の理解を深めるためには、①行政による監視と、②分別を保証する書類などによる証明の2つによって表示の信用を証明するだけでなく、同時に この制度を広く一般に行き渡らせて、消費者を高い認識や理解へと導くことが必要
これが、基本的な考え方です。
もっと分かりやすくまとめますと、表示制度は次の3つの内容が書かれていました。
- 消費者が、分かりやすいようにすることが目的で、
- そもそも日本で流通している遺伝子組換え作物は安全で、
- そのうえでより一般に広く知られることを目指す
そして、ここがポイントかな…と思った点が、「消費者にできる限り分かりやすく」としつつも、「事業者の実行可能性やコストも考慮する」という点。
この両方を調整するのって、かなり難しいのではないでしょうか?
この表示制度が17年間、そのままであったことも、これが理由なのかもしれません。
そして17年間で遺伝子組換え表示をめぐる情勢はどう変わったのか?という項目に続きます。
遺伝子組換え表示制度をめぐる情勢
こちらでは4つの情勢の変化が書かれていました。
できるだけ原文を活かしつつ、要約しますと、
1. 遺伝子組換え農産物の生産・流通実態
日本の食料自給率は継続的に低下していて、大豆や穀物、とうもろこしなどの ほとんどを輸入に頼っています。一方で日本国内では遺伝子組換え農産物は商業栽培されていないものの、世界の作付面積は増加しているだけでなく、複数の遺伝子組換えをかけ合わせたスタック品種も開発・生産されています。
2. 分別生産流通管理の運用状況
遺伝子組換え表示制度では、遺伝子組換え作物を分けているかどうか?という分別生産流通管理の有無について表示基準を定めていますが、消費者庁が2016年に行った調査によれば、輸入元の米国やカナダで実施している分別生産流通管理は適正に機能しており、意図せざる混入率の基準が遵守されているだけでなく、各企業は自主基準で、より低い混入率を達成する努力がなされています。
3. 遺伝子組換え食品の分析技術の向上
機器の性能向上や分析技術の進歩により、これまで検出できないとされた醤油や食用油などの加工食品からのDNA検出ができるようになりました。2016年に消費者庁が行った検査によれば、これまで検出がされなかったコーンフレークの中に遺伝子組換えDNAが検出されましたが、残存量が少ないなどの理由で検査法の確立には至っていません。
4. 遺伝子組換え食品に対する消費者の意識
2016年の調査によると、導入から17年が経っているにもかかわらず消費者の表示制度についての認知度は低く
- DNAなどが検出されない醤油や食用油などの表示が不要なことの認知度は3割
- 分別をしていない「不分別」という義務表示の認知度も3割
- 「遺伝子組み換えでない」の表示の認知度は7割
と、遺伝子組み換え作物を原料とした食品でも表示されない食品があること、そして義務表示である不分別についても知られておらず、唯一認知度が高かった「遺伝子組み換えでない」は、7割が「表示を見たことがある」という結果でしたが、これについては「遺伝子組換え」や「遺伝子組換え不分別」と表示された食品が極めて少ないことが背景にある、とのことでした。
以上ですが、気になったのは「スタック品種」という言葉。
「スタック品種」とは、たとえば害虫への抵抗力ある遺伝子組換え作物と、除草剤への耐性がある遺伝子組換え作物とをかけ合わせたハイブリット品種とのことで、検査をすると遺伝子組換えDNAが2倍量、検出されるそうです。そんな品種まで出てきていることは知りませんでした。