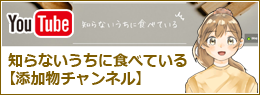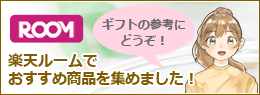遺伝子組み換え表示を見ないで買うと危険?

あなたは「遺伝子組換えでない」という表示を見たことがありますか?
この表示は、2023年4月から激減しました。
なぜか?といえば、これまでは遺伝子組換えの混入が5%以下であれば「でない」と表示ができたのですが、2023年4月からは0%でなければ「でない」と表示できなくなったからです。
これについて調べましたが、ちょっと困ったことになりました。
どの情報も、発信者の主張が含まれたものばかりだったからです。
私はまずオーガニックな情報を知りたいと思いました。
そこで、今回の遺伝子組換え表示制度の変更を決めた消費者庁が開催した「遺伝子組換え表示制度に関する検討会」の報告書を調べてみました。
この記事は動画を作成し、YouTubeにて公開中です
▼チャプター
00:00 オープニング
01:20 表示制度と検討会
03:16 表示制度の考え方
05:12 遺伝子組換えの情勢
07:59 表示制度の方向性(検討会の結果)
10:38 報告書の最後に書かれていたこと
12:42 正しい選択をしよう
遺伝子組換え表示制度と、その検討会とは?
今回、できる限り、そのままの情報をお伝えしたうえで、私が個人として感じたことをお伝えしていこうと思っています。
そこでまず、消費者庁のページにアップされている2018年3月の「遺伝子組換え表示制度に関する検討会」の報告書を読んだのですが…なかなか…文章が分かり辛いと思いましたので、報告書の原文をもとに、できる限り分かりやすく要約していきたいと思います。
まず「遺伝子組換え表示制度」は、2001年から施行された法律で、遺伝子組み換えをした食品には表示が必要であることを定めたものです。
日本では1996年から遺伝子組換え食品の輸入が始まり、当初は、そのような表示の義務はなかったため、なにも表示されずに遺伝子組み換え作物が流通していましたが、これに懸念を示した消費者の要望に応える形で表示が義務化されました。
当時、決まったのが大きく「義務表示」と「任意表示」の2つでした。
- 遺伝子組換え作物を使用している
- 選別していない時に表示をしなくてはならない
- 遺伝子組換え作物を使っていない
- 遺伝子組み換えでないと分別生産流通管理(という選別)をしている時
- 意図しない混入が5%まで
以降17年間、ずっとそのままでしたが、2012年に食品表示を一元化させる法律に向けた「食品表示一元化検討会」で、遺伝子組換え表示制度のあり方について検討すべき、という意見が多くありました。
これを受けて消費者庁は、2017年4月~2018年3月までの約11ヶ月間で、新たな遺伝子組換え表示制度をどうするか?について、消費者、事業者、および学識経験者から構成される「遺伝子組換え表示制度に関する検討会」が開催されました。
次から、この検討会の報告書の内容について説明していきましょう。