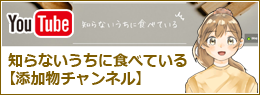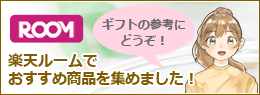遺伝子組み換え表示を見ないで買うと危険?

今後の遺伝子組換え表示制度の方向性
そして、今回決まった遺伝子組換え表示制度の方向性ですが、まず消費者が食品を選ぶ際、容器包装の表示を確認することが一般的であるため、容器包装による情報提供を前提に検討されました。
表示範囲
まず、遺伝子組換えの「表示範囲」については、
表示義務となる品目は、現行制度では遺伝子組換え農産物としての安全性が確認された農産物(8品目)およびこれを原材料とする加工食品(33品目)が表示義務の対象となっていて、遺伝子組換え作物を飼料として使った場合は表示の対象外だったのですが、これについては現行制度の維持が適当、となりました。
また、醤油や食用油、コーンフレークなどの加工食品も、遺伝子組み換えDNAが検査できるようになれば表示義務対象品目に追加する、とのこと。
表示義務
次に表示義務となる条件ですが、現行は原材料および添加物の重量に占める割合が5%以上であるものに限定されていますが、これも現行維持が適当、となりました。
つまり表示対象となる商品の範囲については変わらず、ということですね。
表示方法
また「表示方法」については、
遺伝子組換え農産物およびこれを原材料とする加工食品を「遺伝子組換え」、分別をしていないものを「遺伝子組換え不分別」と表示することが義務付けられていますが、「遺伝子組換え不分別」という表現の認知度が低かったことについては消費者庁で分かりやすい表示方法を検討する、とのことでした。
任意表示の「遺伝子組換えでない」
そして任意表示の「遺伝子組換えでない」は、これまで意図せざる混入が5%までなら表示が認められていたことについては、これを引き下げる要望があったものの、事業者には原材料が調達困難になる可能性や、検査に係る作業量やコストの増大などの問題があるため、現行の「5%以下」のままが適当との判断になりました。
ただ、消費者の誤認を避けるために「遺伝子組換えでない」という表示は「5%以下」から「0%(不検出)」でなければ表示できないという判断になりました。
ここで、2023年4月から「遺伝子組み換えでない」という表示が激減した理由が分かりました。
つまり「遺伝子組み換えでない」表示のほとんどが、混入率が5%以下に管理されたものだったのです。
ただ、これも「任意表示」ですから、そもそも表示されてないものもある可能性があることも覚えておかなくてはいけませんね。
そして、やはり大きな問題は、17年が経っても未だに、遺伝子組み換え表示制度の認知度が低いことであり、これについて消費者庁は、もっとこの認知向上に向けた活動をするよう、提言がされました。
最後に報告書は、こんな内容で締めくくられていました。
報告書の最後のパート

食品表示制度は、消費者が食品に関する情報を得る上で重要であり、消費者が自主的で合理的な食品の選択の機会を確保することが目的とされていますが、現状では
- 大量の作物が、(表示されない)醤油や食用油などの加工食品の原料として輸入されていること
- 個食化などによって容器包装の表示スペースが狭くなっていることなどの問題があります。
報告書では、食品表示制度について消費者側と事業者側の双方が検討したことで、現行制度より一歩前進した制度となった、とありました。
この検討会を経て、遺伝子組換えに関する表示がより消費者の選択の幅が広がることに繋がり、今後は消費者庁が報告書に示した方向性に沿いながら、諸外国の情報収集も行いつつ、基本的な考え方である「消費者にとって自主的かつ合理的な食品の選択ができるようになるための制度にするよう、万全を期すことが求められる。」といった内容で、11ヶ月にわたる検討会の報告書は締めくくられていました。
いかがだったでしょうか?
11ヶ月もかけ話し合った結果が、「たったこれだけ?」と思った方もいるかもしれません。
ただ、誤解を生まないようお伝えしますと、検討会はほぼ毎月、10回にわたって行われました。
事業者側(メーカーや流通業界を代表する企業・団体)が意見を述べ、消費者側とそれぞれに意見を交わせたという経緯が分かると、かなり結論を導くことが難しかったことは想像できると思います。
気になる方は、次ページの「参考リンク」から検索してみてください。
| メーカーや流通業界を代表する企業・団体 | 消費者側 |
|---|---|
| 日本植物油協会 日本醤油協会 日清シスコ株式会社 三好食品工業株式会社 ハウス食品株式会社 ライフコーポレーション株式会社 イオンリテール株式会社 三井物産株式会社 日本生活協同組合連合会 | 主婦連合会 日本消費者連盟 |